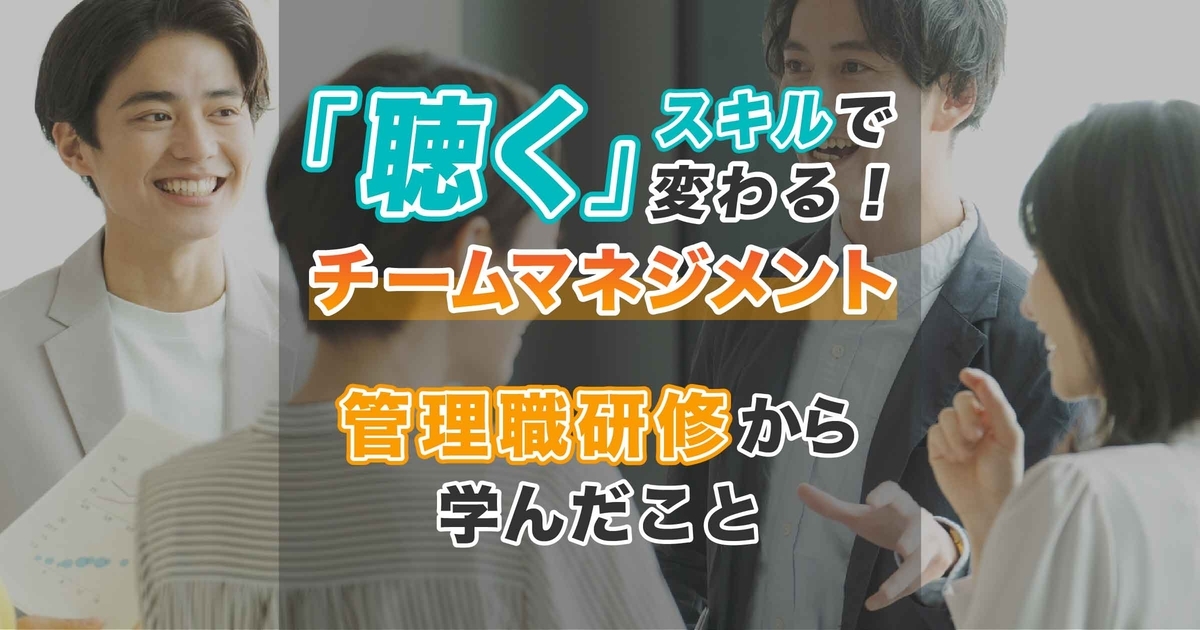
はじめに
こんにちは、開発チームの池田です。私は新米エンジニアリングマネージャー(EM)として、メンバー育成に不安を感じることは少なくありません。
技術的なスキルは高くても、ピープルマネジメントとなると自信がない…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
スパイダープラスでは、管理職者の成長をサポートするための研修プログラムを定期的に実施しています。
今回は「聴く」スキルに焦点を当てた研修に参加する機会がありました。
この研修で学んだのは、単なるコミュニケーションテクニックではなく、チームの心理的安全性を高め、メンバーの成長を促進するための本質的なスキルです。
特に技術組織において、「聴く」スキルがいかに重要か、そして具体的にどのように実践すればよいのかについて、多くの気づきがありました。
この記事では、研修で学んだ「聴く」スキルの重要性と実践方法について共有します。
新米EMの方はもちろん、ベテラン管理職の方にとっても、日々のマネジメントを見直すきっかけになれば幸いです。
メンバーの声を『聴く』ことの大切さを学ぶ研修について
今回の研修の目的は以下の2点でした。
- ピープルマネジメントにおける「聴く」ことの大切さを知る
- 「聴く」ことのコツを知り、実践できる状態となる
参加者は各部門の管理職約50名で、エンジニアリング部門からも多くのマネージャーが参加していました。
研修は講義パートとワークショップパートに分かれ、合計約3時間のプログラムでした。
研修の背景には、組織のパフォーマンス向上のためには「心理的安全性」の構築が不可欠であり、その基盤となるのが「聴く」スキルであるという考え方があります。
特に技術組織では、問題解決に焦点が当たりがちですが、その前提となるメンバーの声を「聴く」ことの重要性が強調されました。
非言語×言語で学ぶ、「聴く」スキルの講義
研修は、元ヤフーで人事顧問の菱沼 恒毅さんを人事コンサルタントとして講師に招き、講義が行われました。
講義では、組織のパフォーマンス向上のためには、心理的安全性の構築が不可欠であり、その基盤の1つが「聴く」スキルであることが説明されました。
効果的に「聴く」ためのスキルとして、非言語スキルと言語スキルの2つの側面からいくつかの文献の解説がありました。
**非言語スキル**としては以下の4つが紹介されました:
- 時間と場所を決める:適切な環境設定の重要性
- 眉毛で反応する:相手の話に関心を示す方法
- 沈黙に強くなる:相手が考える時間を尊重する
- 7色の相槌:様々な相槌で相手の話を促進する
**言語スキル**としては以下の5つが紹介されました:
- 正直でいる:偽りのない反応を示す
- 返事は遅く:即答せず、考えてから応答する
- オウム返し:相手の言葉を繰り返して理解を示す
- 詳しくきく:質問を行う
- 「分からない」を使う:理解できないことを素直に認める
「聴く」スキルがマネジメントの根幹を成す重要なスキルであり、継続的な実践が必要であることを学びました。
「聴く」スキルが単なるコミュニケーションテクニックではなく、マネジメントの本質に関わる重要なスキルであることが強調されていました。
ワーク 〜「聴く」スキルを実践してみる〜
講義の後には、実際に「聴く」スキルを実践する個人ワークとチームワークが行われました。
個人ワークでは、メンバーについて知っていることを言語化し、これまでにどれだけ「聴く」ことができているかを確認するワークが行われました。
チームワークでは、他のマネージャーがどういった解像度でメンバーの声を聴いているかを意識するための土台づくりのためのワークが行われました。
個人ワーク
最初のワークは「メンバー理解度チェック」と題された個人ワークでした。
このワークでは、自分のチームのメンバーについて「知っていること」を以下の8項目に沿って言語化していきました。
- 最近嬉しかったこと
- 最近悲しかったこと
- FY24下期評価の納得度
- 評価フィードバックを受け、行動変容している内容
- 評価フィードバックを受け、行動変容が物足りていない内容
- 強み
- 弱み
- キャリア志向
各項目について、メンバー一人に対して答えられるかどうかをチェックしていきます。
このワークの目的は、自分がメンバーの声をどれだけ「聴けている」かを客観的に確認することです。
また他のマネージャーがどういった解像度でメンバーの声を聴いているか意識することも目的となっていました。
実際に行ってみると、仕事に関する項目(評価の納得度、強み、弱みなど)については比較的言語化しやすかった反面、プライベートに近い項目(最近嬉しかったこと、最近悲しかったことなど)についてはあまり言語化できなかったです。
このことはメンバーとコミュニケーションが足りていないということの表れであり、メンバーについての理解が足りていなかったことを実感しました。
仕事に関する項目とプライベートに近い項目をバランスよく把握することで、メンバーを良く知ることが重要であることがわかりました。
チームワーク
次に「聴く」スキルを実践するワークを、組織を横断した数名ずつのチームに分かれて行いました。
ひとつめは上司役とメンバー役となり自組織の課題をテーマに1on1デモを行いました。
他の2名はそれを見て、「聴く」に関してフィードバックを行いました。
1on1デモでは、「聴く」スキルを実践することの難しさを改めて実感しました。
沈黙の時間を作ることの難しさであったり、質問の仕方の重要性や上司である自分が話し過ぎになってしまっていたことを改めて感じました。
このワークを通じて「聴く」スキルを実践的に活用し、参加者が互いにフィードバックを行うことで、スキルの定着を図ることが重要であることを実感しました。
ふたつめは以下のテーマについてチームディスカッションを行いました。
-
個人ワークの感想
-
コミュニケーションの悩み
-
経験した「良い」1on1のシェア
-
経験した「嫌な」1on1のシェア
-
良い1on1をするために今日から意識すること
他組織のマネージャーとのディスカッションだったため、その組織特有の悩みであったり、逆に異なる組織であっても同じ悩みを持っていることがわかりました。
また今後の自組織のメンバーと1on1を行う際に、意識して実践すべきことの確認にもなり、とても学びのある時間となりました。
おわりに
新米EMとして、メンバー育成に不安を感じていた私にとって、今回の「聴く」スキル研修は大きな学びとなりました。
特に印象に残ったのは、「対話の質がメンバーの成長速度を決める」という言葉です。
いくら優れたフィードバックのテクニックを持っていても、メンバーの状況や考えを正確に理解していなければ、その効果は限定的になってしまいます。
エンジニアリング組織では、技術的な課題解決に焦点が当たりがちですが、人と人との対話の質がチームの成果を大きく左右します。
「聴く」スキルを磨くことは、単なるマネジメントテクニックの向上ではなく、組織文化の醸成にもつながるのです。
研修で学んだスキルを日々の1on1で実践し、メンバーの声に真摯に耳を傾けることで、チームの心理的安全性を高め、メンバー一人ひとりの成長を促進していきたいと思います。
皆さんも、明日からの1on1で「聴く」ことを意識してみてはいかがでしょうか?
小さな変化から、大きな成長が生まれるかもしれません。